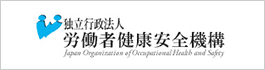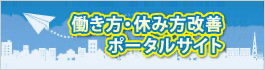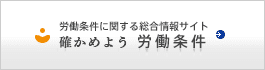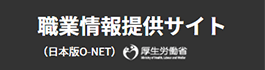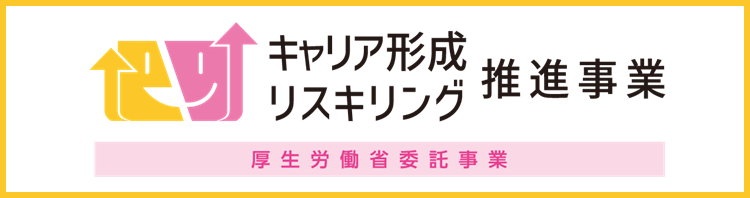治療と仕事の両立支援コラム
こちらのページでは記事形式で
コラムをご覧いただけます。
2023.3.31
労働者としての人生を救う
「見つけて・伝えて・繋ぐ」こと
~さんぽセンターとの連携の事例から~
佐藤 朋江 氏
はじめに
想像してみて欲しい。ここは金属加工業が地場産業の地方都市。ある5月の暖かい日,あなたは病院にいて,白衣を着て椅子に座っている。目の前には車椅子に乗った50代ほどの男性が途方に暮れた様子であなたを見ている。かつて金属加工職人だった彼は,今病気のために歩けず,手もしびれて、人生の岐路に立っている。そして問う。「私はどうしたらいいのでしょうか」と。
これは実話である。白衣を着ていたのはまさに私であり,彼(Aさん)は私の担当患者であった。彼だけではない。この時,私も彼と同じくらい途方に暮れていた。しかし,この面談の半年後には,彼が改造車で職場に乗り付けてリハビリ復職を果たすことになるとは,二人とも夢にも思っていなかったのである。
さんぽセンターとの出会い
話はこれより約1年前にさかのぼる。Aさんは神経免疫疾患を発症した。治療は奏功したが重度後遺症を残し,これ以上の改善は見込めなかった。サッカーが趣味だった彼は,両下肢麻痺のために車椅子生活となり,自律神経障害により導尿や排便処置が必要だった。リハビリを重ねて自宅に戻ったが,その先の未来は描けなかった。勤めていた金属加工業会社の社長は,親方気質でAさんの職場復帰を望んでいたが,彼もまたどう支援すべきか思いあぐねていた。私はと言えば,神経内科医として長年勤務していたものの,本格的な就労支援に関わったことはなく,同じように逡巡していた。
この状況に一筋の光明が差したのは,ある電話がきっかけだった。私は以前産業保健総合支援センター(以下「さんぽセンター」)の保健師Kさんと知り会う機会があった。はじめて聞くさんぽセンターという言葉に戸惑う私の前で,彼女は大変な勢いでさんぽセンターの意義や思いを熱弁し、最後に「就労を希望されている症例をぜひご紹介頂きたいと思っているんです!」と熱く迫って来るのであった。途方に暮れるAさんを前にした時に、ふとあの熱いKさんの言葉を思い出したのである。何かのきっかけになればと、軽い気持ちでKさんに電話した後、状況は大きく動き始めた。
患者である前に、一人の労働者として
電話の後、さっそくさんぽセンターから保健師のLさん、復職支援員のMさんがやってきた。彼らは私やリハビリスタッフと一緒に復帰に向けた段取りの草案を作り、それを更にAさんや社長のところへ持っていき、現場を実際に見ながら、バリアフリーや室温管理などの職場環境改善策を提案した。加えて使える社会保障制度や企業支援制度の活用も提案した。Aさんの復職にあたり彼らが病院と会社の双方を行き来する中で、実は社長は最初から他の工場員達がバラバラに行っていた事務作業をAさんが一括して担当することで、業務を効率化できてよいのではないかと考えていた事も判明した。
このようにして順調に改造車取得、リハビリ復職と進み、雪が降る前の11月に彼は改造車を自在に乗り回し、無事に職場復帰を果たしたのである。社長の忘れられない一言がある。Aさんの同意を得て行った社長同伴の病状説明において、全てを理解した上で「それでも、僕は彼がいつかは歩けるようになると信じて、一緒にやっていきたいと思っているんですよ」と笑顔で話したのである。彼にとって社員は家族であった。そして、私の前では患者であった彼は、その前にこの会社の1人の労働者であり、地域社会の一員だったのである。彼はその後、私の予想を超えた回復を続け、徐々に歩行が可能になり現場作業にも少しずつ復帰している。更に自ら社長や会社の社会保険労務士と収入や勤務内容について交渉し、よりより労働環境をお互いに作る事が出来ている。社会の一員であり続けるということ、役割を持って生きるということがどれほど人に力を与えるのか、ということをAさんは私に教えてくれたのである。
病気の後に続く人生も救うために
治療の結果、障害が残るという想像もしなかった状況になった時、患者自身及び職場の人が途方に暮れるのは当然である。そして両者の異なるニーズを医療者が理解し調整することも、また同じくらい困難なことである。考えてみれば医療者と企業は同じ社会にありながら、ずいぶんと成り立ちも目指すところも異なる。まるで川を挟んで対岸に位置する別の国のように感じられることもある。その間を流れる川の中で、患者は今にも溺れそうになっているのである。そこで必要なのは、その川を自在に泳ぎ二つの国を行き来して両者の言葉を通訳し、双方が状況や課題を理解するのを助け、全員が納得する方向に患者を送り届ける船頭の役割を果たしてくれる人である。さんぽセンターはまさにその役割を果たしてくれた。それぞれの専門性による限界があるからこそ、さんぽセンターのような福祉のみならず社会保障にも長けた、異なる分野の専門家とネットワークを構築し、当事者を中心として、医療、社会福祉の三者で連携することに意義がある。結果として、より患者に利する結果を生み出すことが出来る。
今回のケースを通して私が何よりも感じたのは、医療者が「見つけ、伝え、繋ぐ」ということの重要性である。真面目な患者ほど「職場に迷惑をかけてはいけない」と、焦って離職してしまう。そのような今にも川で溺れつつある患者を見つけ、支援が可能である事を伝え、そして適切な専門家に繋ぐという事が出来るのは、臨床の最前線で患者に接する私たち医療者である。ためらわず、気軽に「仕事で何か困っていませんか?どうしていくか相談してみませんか?」と目の前の患者に声をかけて欲しい。その一言がその人らしい暮らしを守り、そして一人の労働者としての人生を救うことに繋がると信じている。

佐藤 朋江
新潟県立燕労災病院 神経内科医長
2007年新潟大学医学部医学科を卒業
2009年下越病院にて臨床研修を修了
2018年新潟大学脳研究所病理学分野にて博士課程を修了
2018年総合内科専門医取得
2023年日本神経学会指導医取得
新潟県内の複数の病院で神経内科医として勤務し、2018年より現在の燕労災病院にて勤務