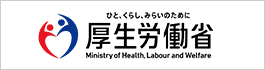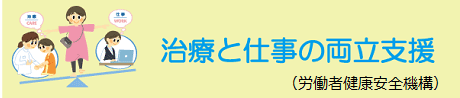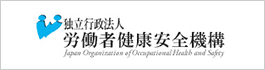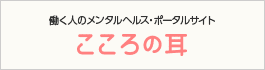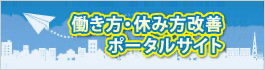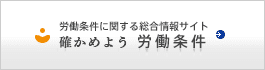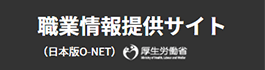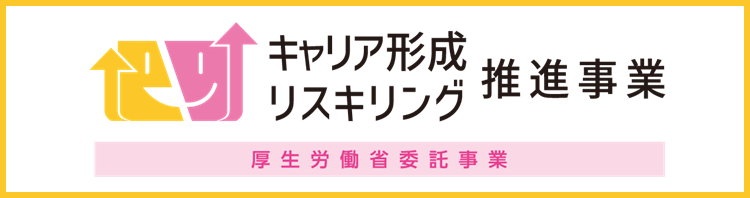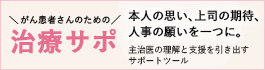両立支援の取組事例
「働く意思がある限り雇用し続ける」労働者に寄り添った両立支援
株式会社アスター

総務部 監査役 青木 峰夫 氏
- 会社名
- 株式会社アスター
- 所在地
- 秋田県横手市柳田12-3
- 事業内容
- EV用、ドローン用モーターの開発、製造、販売
- 設立
- 2010年1月
- 従業員数
- 116名(2022年9月現在)
- 平均年齢
- 44.9歳 /男女比 男性6.2:女性3.8
- 産業保健スタッフ
- 2名
2010年、前身であるアスター工業株式会社秋田工場の閉鎖の際に建屋と従業員を引き継ぎ、「株式会社アスター」は設立されました。従来銅線を巻いていたコイルを板状の銅やアルミニウムで成形することに成功し、ASTコイルという独自の積層技術で開発したコイルを取り入れた新型高性能モーター「ASTモーター」を開発しました。「ASTモーター」の技術を発電機やモビリティ分野に応用することにより、株式会社アスターは地球環境に大きく貢献することができます。さらには医療分野や産業機器分野などでも活躍が期待されています。両立支援においては治療に専念でき、先の就業に対する不安を解消させる環境づくりで経験者が長く仕事に従事できるよう支えています。
代表取締役は起業当初から経営的に苦しい時期を共に過ごしてきた労働者を家族のように思っています。その考えがあるため、雇用した労働者が自社で働く意思がある限り、どんな事情があっても雇用し続けると決めています。両立支援に取り組んでいるのは代表取締役のトップダウンによるものです。
両立支援においては本人が治療に専念でき、先の就業に対する不安を解消させる事が大切です。また、社員が習得し築き上げてきた技術、力量、ノウハウを継続し、次の世代に伝承しています。そうした過程で重要となる経験者が長く仕事に従事できる環境づくりを行っています。
代表取締役の方針で地元で働いてくれる従業員を大切にする事は創業当初からの会社風土としてあります。
労働者とのコミュニケーションを大切にし、働く意思がある限り雇用し続けるという思いを労働者に伝えています。また、代表取締役に近い位置にいる総務・経理の担当職員が代表取締役の思いを共有して病気になったときには相談するよう労働者に伝えています。
〈相談窓口〉
新たに相談窓口等を設けることはなく、直属の上司や総務・経理関係の担当職員が相談窓口になっています。
〈休暇制度・勤務制度〉
労働者個人の症状や要望に合わせて設定しています。
〈支援の流れ〉
労働者から申出があった場合には上司や総務・経理担当職員がまず対応をし、その後代表取締役に判断を仰ぐことになっています。代表取締役が主治医の診断結果、労働者の要望をもとに労働者の思いを尊重し、支援内容を決定します。会社トップ自ら、その対応について迅速に即決即断する体制、会社風土があり、その中で本人との話し合いの中で最善の支援策を臨機応変に決定しています。
〈個人情報の保護〉
症状や治療の状況等の疾病に関するプライバシーに配慮すべき情報であることから厳重に管理しています。相談窓口になる上司、総務・経理担当者にも情報漏洩しないよう教育しています。
■50代男性社員の事例
入社当時から品質管理業務に従事していた社員が3年前に肺の病気で1年間入院しました。退院後は基礎体力をつけて復帰するために、期間を定めることなく自宅休養を行いました。新たな職場、業務は本人の負担となるので、本人がもともと在籍している部署で得意とする仕事に復帰するよう配慮しました。休職期間中は仲間が仕事のカバーをし、合わせて中途社員を採用して対応しました。復帰後、再発により現在も病院に入院中ですが、会社側としては、本人の早い復帰を待っています。(継続雇用中)
秋田産業保健総合支援センターの産業保健相談員に相談しています。
総務部担当者が秋田産業保健総合支援センターの研修を受講、また障害者職業生活相談員資格認定講習も受講しました。
研修等による意識啓発等はしていませんが、社員からの申出に対し会社側が状況を把握して双方にとってベストな対応を臨機応変に行っています。
枠にはまった制度にとらわれ事務的な処理にならないように、社員一人一人の状況をよく把握した上で、最善の支援策を決めていきたいと思っています。
取組事例一覧