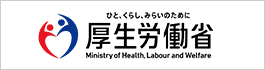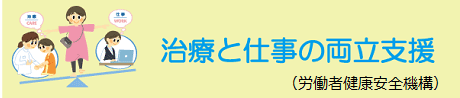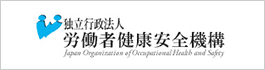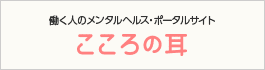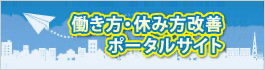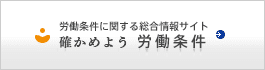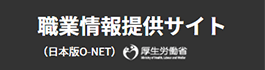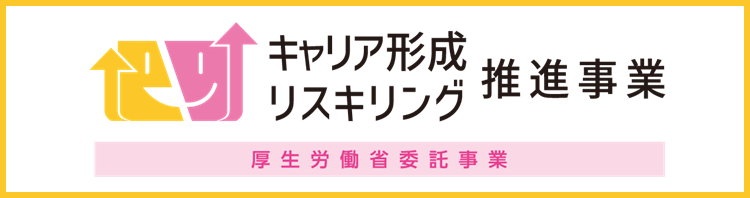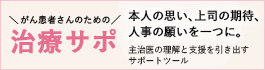両立支援の取組事例
治療と仕事の両立支援は特別なことではありません
日本電気株式会社(NEC)
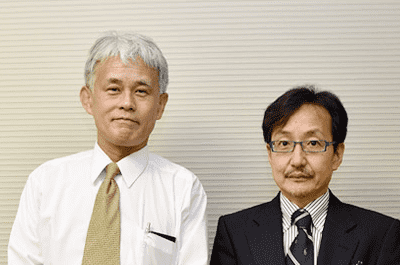
(写真左より)
健康管理センター シニアマネージャー 兼 総務部シニアエキスパート
高橋 亨氏
健康管理センター医療主幹 兼 産業保健サポートセンター長 兼
本社健康管理センター長
医学博士 労働衛生コンサルタント
柿沼 歩氏
- 会社名
- 日本電気株式会社(NEC)
- 所在地
- 東京
- 事業内容
- 電機
- 従業員数
- 21,444名(2017年3月末現在)
- 産業保健スタッフ
- 約100名
NECはグループをあげてICTの力を活用した価値の創造を進める企業だ。従業員数は連結で9万8000人超。その健康管理を、100名近くいる産業保健スタッフが支えている。
治療と仕事の両立支援に対するNECの考え方は「これまでの取組の延長線上にあります」と高橋氏はいう。 メンタル不調に陥った人がいれば、その治療を見守り職場復帰を支えてきたのと同様に、がんなどに罹患した社員のサポートも行っているのだ。 「これらを特別なことだとは考えていません」と柿沼氏もいう。「NECはダイバーシティを推進していて、たとえば障害のある人、難病を抱えている人などすべての社員にとって働きやすい環境づくりを目指しています。両立の支援はそのうちの一つに過ぎません」

「なかには、年休を使えば治療ができるので会社には知らせないという人もいるようです。ただ、私たちにはこれまで支援してきた経験がありますから、その人にとって初めて遭遇する悩みや不安をきっと減らすことができるはずです。 ぜひ相談してほしい」と柿沼氏はいう。上司に罹患を開示するかどうかは、原則、本人の判断になるが、「開示した後は健康管理センターだけではなく、人事や上司とチームを組むことができ、より効果的な支援が可能になります」(柿沼氏)。 このようなチームでの取組もNECの特徴と言えるだろう。
社員の中には、命よりも仕事を失うことを恐れているようにさえ見える人もいる。仕事への強い責任感を持ち、働くことで活力を得ているような社員ほど仕事から離れられないと考えるようだ。 「しかし特にがんの場合は命に関わりますから、治療を最優先してほしい。健康回復のために仕事を休むことで不利益を被ることはないと知ってほしい」と柿沼氏はいう。
職場への復帰支援は2010年に改訂した「職場復帰支援プログラム」に沿って行われるが、プランは一人ひとりの、症状、仕事の内容、プライベートも考慮してベストな道を探すことになる。元の職場には戻るのが難しくても、ほかの職場でなら仕事ができそうなら、配置転換も視野に入れる。
ただ、産業保健スタッフにも悩みが多い。その要因は「真面目な社員が多いこと」だと高橋氏。
一刻も早く職場に戻ろうとする人が多く、その意志を汲んだ主治医が復職にゴーサインを出したと見られるケースが少なくないのだ。
産業保健スタッフ側は、通勤の負担や業務内容などを勘案し、時としてそのゴーサインにストップをかけざるを得ない。「板挟みになることはあります」と柿沼氏。

また、治療をする本人の上司もどう対応するべきか悩むことは少なくない。部下ががんなどになったと知ったとき、治療に専念して欲しいと考える一方で、できた仕事の穴をどう埋めるのかにも頭を悩ませることになるからだ。 「こういったことがあるので、人事も含めたチームでの対応が必要になります」と高橋氏はいう。この問題を解決するには「病気になって業務から離れなければならない人が出てくることを前提とした組織作りや働き方の改革が必要なのかもしれない」と柿沼氏はいう。

一方で柿沼氏は、こういったチームでの支援は「大企業だからできることと言われればその通り」という。
「しかし、中小企業では両立支援は無理ということではなく、企業の規模に合わせた融通のきかせ方やできることがあるはずです。いずれにしても必要なのは、両立支援への経営者の理解ではないでしょうか」と指摘する。
NECは、両立支援はダイバーシティ推進の一環と考えている。障害のある人、メンタル不調 の人、そしてがんなどの治療が必要な人に対しても、同じ発想で向きあっている。